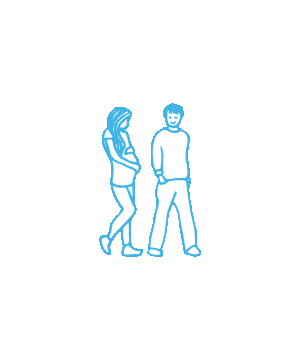
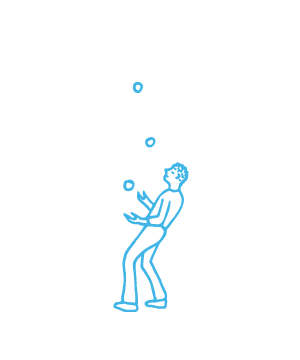

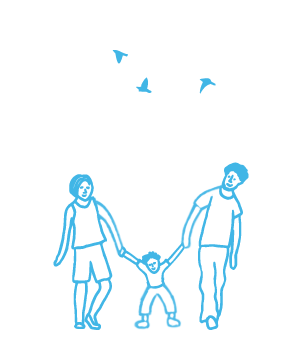
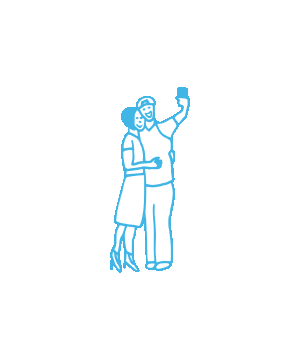
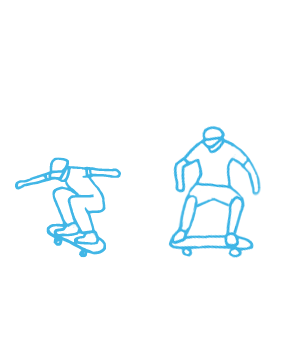
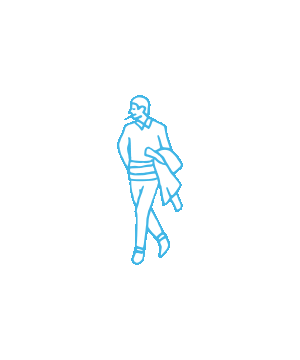
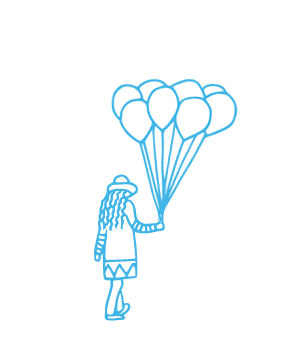
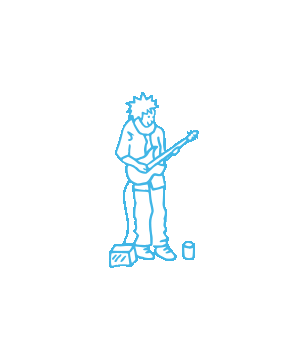
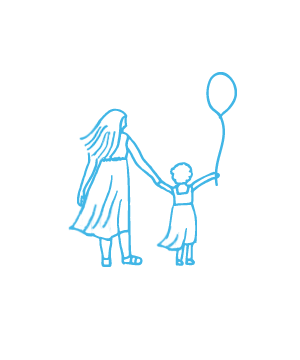

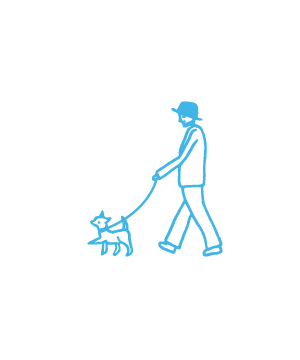
北京ストアコンパリゾンレポート第1回 盒馬鮮生(フーマーションシェン)
株式会社エイジス 営業推進室の菅沼です。
中国のお買い物事情は、どうなっているか。「ニューリテール」とは・・・。いくつか店舗視察してきた北京の流通事情を、複数回にわたってご紹介いたします。
☆盒馬鮮生(フーマーションシェン)
言わずと知れた「ニューリテール」代表的企業、その京成店にいってきました。
お客様が買い物をし、購入した食材をその場で料理人に調理してもらって食べることができたり、生きたまま水槽で管理されている鮮魚を選ぶ、見事に並べられた迫力ある売場を目で楽しむといったリアル店舗としての楽しさも十分にありますが、このお店の本質は、食品デリバリーをメインサービスとするNETスーパーと言えます。
オンラインで買い物をして、店舗から3キロ以内であれば30分以内に無料で宅配してもらえますし、店頭で商品を選んですぐに持ちかえりたくない場合でも、フーマーのアプリでQRコードを読み取ってオンラインのカートに入れ、あとで届けてもらうこともできます。 まさに”O2O(Online to Offline)”です。
保冷バッグを両手に抱え、店舗で商品をピッキングしている従業員は、一人や二人ではありません。ピッキングされた保冷バッグは、店内天井にあるベルトレーンで次々と運ばれていきます。その光景も目で楽しむことができ、リアル店ならではの来店客へ魅せる”工夫”がありました。
価格表示はデジタルプライス、生鮮にいたるまで手書はありませんでした。価格変更はNETも売場も、一括集中管理されていることが伺えます。また基本は定番陳列のみで、過剰な圧縮陳列も、無駄なPOPも無いことから、店舗オペレーションの生産性は高いと推測できます。
単身、共働き世帯が多い北京の市場を反映して、カット野菜やチルド加工食品の個包装もラインナップが充実しており、清潔感のある売場が印象的でした。
酒類も豊富、日本酒など下手をすれば日本のスーパーより充実した品揃えかもしれません。
バックヤードを持たないのも特徴で、店舗用地が既存店と比べ、少なくて済みその分、立地にこだわった出店ができます。
単品在庫管理上でも、店頭定番のみに商品が存在するので、管理が容易であり、商品のオンライン上の在庫数と店頭の在庫数は、リアルタイムで一致しています。
また「品出し」というバックヤードからの商品移動業務も存在しません。その代償ではありますが、売場欠品が頻繁に発生します。 日本のスーパーマーケットの常識からみれば、フーマーの売場は、”ありえない”ほど売場欠品があるように見えます。しかし、お客様も従業員も、全く気にする人はいません。
フーマーは、まずオンライン購入ありきでビジネスを組み立てており、リアル店舗は”劇場”的な役割のみと割り切っているからこそ、売場欠品を大きな問題と捉えていません。
新鮮、安全、清潔、楽しく飽きさせない売場、配達にかける工夫など、自社の取り組みを十二分にアピールする売場で、来店したお客様に愉しい買い物体験をしていただき、”フーマー”というブランドへの信頼を植えつけます。
するとお客様は次回以降、来店せずとも「フーマーなら大丈夫」と信頼して、食品をNETで繰り返し注文いただけるようになります。
店舗にお客様が再来店することが、リピートの絶対条件で無い仕組みの中では、多少の売場欠品など些細な問題としか映りません。(というかNETからは見えません)
お客様に店舗へ来ていただかないと、勝負できないリアル店舗メインの企業と違い、フーマーはリアル店舗でお客様の信頼を勝ち取り、「あとはオンラインで、いつでも安心して注文してください、ご存知のとおり安全で便利ですよ」と、誘導すれば良いのです。
この考えはリアル店舗から商売をはじめた従来の小売業と比べ、真逆の発想です。 リアル店舗での売場欠品は「わざわざ来店してくださったお客様」を裏切る行為であり、お客様を失う可能性がある危険な機会損失と考える小売企業が一般的です。
日本のNETスーパーは、既存リアル店舗に間借りして運用していることが多く、 ”売場欠品させてはならない”という不文律下でのピッキング運用を暗に求められ、きわめて非効率なオペレーションに陥っていたり、NET上で在庫があるように見えても、実際注文すると欠品だらけで、クレームまみれの残念なNETスーパーになってしまったりすることが、しばしばあることを考えると、思い切った「割り切り」が必要なのかもしれません。
決済は「AliPay」のみ可能で、以前は現金不可でしたが、中国当局の指導もあり、現金が使えるレジが供えつけてありました。
「AliPay」での支払いを前提とすることで、お客様の購入情報が、リアルタイムで得られるというメリットがあり、「どの顧客がいつ、どこで、何を買ったか」データと利用歴などをもとに、個人に信用情報を付与するのが「ジーマクレジット」と、アリババグループ全体で金融連携しています。
この個人情報データは、これからのデータドリヴン時代において、莫大な価値を有するデータとなることは、疑いようもありません。
余談ですが、私が事前に準備した「WeChatPay」はライバル企業のテンシェント製なので使えず、北京で現金で買物した数少ない店舗となりました。
生鮮食品という、直接人の口に入るデリケートな商材は、”自分で見て選ぶもの”であり、NETでの生鮮食品購入には、懐疑的な日本人が、現在はまだまだ多いと思います。
「食品をNETで、繰り返し購入する安心と信頼を築くための、劇場型リアル店舗」
フーマーが、中国での食品購入の常識を変えたように、日本でも「ニューリテール」が出現する日を楽しみに待っています。
☆なんでもスマホで「Pay」決済
北京でのお買い物事情で一番驚いたことは、キャッシュレス決済の浸透度の高さです。なんでもスマホアプリの「Pay」で解決できます。
日本でも消費増税と合わせて、注目が集まっているキャッシュレス決済ですが、北京はその最先端を走っている都市です。
都市部に限ると人口に対する普及率は、98.3%にまで成長しているそうです。日本の18.4%(2019年5月)に比べると驚異的な普及率です。スーパーマーケットでのお買い物も、ファストフードでのお食事も、足つぼマッサージなどのサービスも、みんなスマホ決済です。

弊社の現地男性従業員と待ち合わせすると、彼はお財布一つ持たない”手ぶら”で現れました。日本の常識だと考えられません。普通、男性とはいえ財布くらいは携帯しているものですが、彼はスマホ以外持っていませんでした。
聞けば、最近はスマホを持って歩けば、アプリで決済はすべて解決するので、財布や現金を持つことは、リスクでしかなくなったとのこと。
現金持たなくていい、カード持たなくていい、ポイントカードや診察券であふれかえる財布を持たなくていい。えっすごい、なにそれ、ストレスフリーですね。
確かに街で人を観察すると、男性でセカンドバックやボディバックを持っているのは、あきらかな外国人か、地方から出てきた旅行者しかいない雰囲気です。みんな基本は「歩きスマホ」で、ポケットに財布らしきものは見当たりません。
なるほど、合理的です。(歩きスマホはダメですが)
アリババの「支付宝(Alipay)」と「微信支付(WeChatPay)」が中国電子決済の二大巨頭らしく、現地に銀行口座を持つ友人に早速送金していただき、私も早速「WeChatPay」を入手しました。これで最強です。
思えば到着日、タクシーで現金で払おうとした際、運転手がダッシュボードやらなにやら引っ掻き回して、やっとのことでお釣りを集め、
「なんか1元足りないけど、俺のせいじゃないよね」
と若干キレ気味にゼスチャーしてきた際、ちっとも悪くないのに、なぜかそのまま笑顔でタクシーを降りてしまったチキンな私には、大変うれしいアイテムです。
ただ、スマホがNETに繋がらなかったり電池切れするとアウトなので、100元程度の現金は、どこかに持っておくことをオススメされました。
現地営業マンいわく現金を持たない状態で、NETに繋がらなかったり、スマホの電池が切れそうになると、とてつもない恐怖を味わえるそうです。
(味わいたくない・・・)
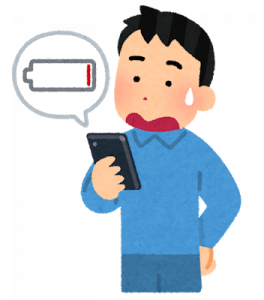
「WeChatPay」のおかげで、両替した現金がほとんど手元に残ってしまったミステイクも、旅行下手な私には、よい勉強になりました。
ただ、これほど電子決済が普及しているのは、都市部近郊だけらしく、地方ではまだまだ現金での決済も残っているようです。
観光地である地下鉄天安門東駅では、現金切符購買機にあきらかに”おのぼりさん”な国内旅行者が、列を成していたり、電子決済専用機前でガイドさんが、電子マネーでの切符購入を案内したりする光景が見られました。
以上










